観察は、作業療法のすべての場面に関わる基本的な力です。
一方で、「評価」「判断」「介入」との違いや関係が曖昧なまま、経験則で使われていることも少なくありません。
本記事では、作業療法における観察を構造的に整理し、記録・目標設定・臨床推論まで一貫して使える視点をまとめます。
作業療法で「観察が苦手」と感じてしまう本当の理由

作業療法における観察の苦手意識は、能力不足ではなく「観察の捉え方」に原因があるケースがほとんどです。
この章では、なぜ観察しているはずなのに判断や介入につながらないのか、その構造を整理します。
観察が止まってしまうポイントを理解することで、次の章以降で扱う「観察の使い方」が明確になります。
見ているのに残らない観察が起きる仕組み
観察が苦手だと感じるOTの多くは、実際には「見ていない」のではなく「見た情報を保持できていない」状態にあります。
表情、姿勢、動作、反応などをその場で確認していても、それらが頭の中で整理されないまま流れてしまうためです。
この状態が起きる理由の一つは、観察が目的を持たずに行われていることです。
「とりあえず全体を見る」「変化がないか確認する」といった曖昧な意識では、情報は点のまま残ります。
結果として、記録を書く段階やカンファレンスの場面で「何を見ていたのか説明できない」状況になります。
観察は量ではなく、意味づけができて初めて残ります。
何のために見ているのかが定まらない限り、どれだけ丁寧に見ても観察は積み上がりません。
「センスがない」と思い込んでしまう思考の罠
観察がうまくいかない経験が続くと、「自分には観察のセンスがない」と考えてしまいがちです。
しかしこの認識は、観察の結果だけを見て原因を内面化している点に問題があります。
周囲の先輩OTが的確な判断をしているように見えるのは、観察のセンスが優れているからではありません。
多くの場合、観察した情報をどの枠組みで整理するかを知っているだけです。
センスだと思い込んでしまうと、「どう改善すればいいか」が見えなくなります。
その結果、観察を増やす、細かく見るといった方向に努力が向かい、かえって混乱が強まります。
本来必要なのは、観察の量ではなく、使い方の理解です。
観察が評価や介入につながらない瞬間に起きていること
観察が評価や介入につながらないとき、多くの場合「観察」と「判断」が切り離されています。
見た事実をどう評価し、どのような仮説を立てるのかが整理されていない状態です。
例えば、動作が不安定という観察があっても、
それが身体機能の問題なのか、環境要因なのか、心理的な影響なのかが結びつかなければ次の一手は出ません。
このとき起きているのは、観察が単なる情報収集で止まっている状態です。
観察は評価の前段階であり、判断を生むための材料です。
この位置づけが曖昧なままだと、観察は増えても臨床は前に進みません。
「何を見るか」より先に整理したい観察の目的と意味

観察というと「どこを見るか」「何をチェックするか」に意識が向きがちです。
しかし実際には、観察がうまく機能するかどうかは、見る内容よりも目的の整理で決まります。
この章では、観察を単なる確認作業で終わらせず、評価や介入につなげるための土台となる考え方を整理します。
観察は情報収集ではなく仮説づくりの材料
作業療法における観察は、情報を集めること自体が目的ではありません。
本質的な役割は、「この人はなぜ今このような状態なのか」という仮説を立てるための材料を得ることです。
例えば、立ち上がり動作が不安定という観察があった場合、
それだけでは評価にはなりません。
筋力の問題なのか、恐怖感なのか、環境設定の影響なのかといった仮説が浮かんで初めて、観察は意味を持ちます。
仮説を前提に観察すると、見る視点は自然と絞られます。
「全部を見る」状態から、「この仮説を確かめるためにここを見る」という観察に変わるため、情報が残りやすくなります。
評価・判断・介入と観察がズレると起きる問題
観察の目的が曖昧なままだと、評価や介入との間にズレが生じます。
よくあるのは、観察内容と介入内容がかみ合っていない状態です。
例えば、表情の硬さや反応の乏しさを観察しているにもかかわらず、
介入では身体機能面だけを強化し続けてしまうケースです。
この場合、観察は行われていても判断に反映されていません。
観察・評価・介入はそれぞれ独立した作業ではなく、連続したプロセスです。
観察が評価に、評価が判断に、判断が介入につながる流れを意識することで、
「何をしているのか分からない介入」から抜け出しやすくなります。
ICF視点で整理すると観察の軸が一本になる理由
観察の視点が散らばってしまう場合、ICFの考え方が有効です。
ICFは、心身機能・活動・参加・環境因子・個人因子という枠組みで人を捉えます。
この枠組みを使うことで、
「今見ているのはどのレベルの情報か」を整理できます。
例えば、動作のぎこちなさは活動レベル、
表情や意欲の低下は心身機能や個人因子、
環境設定は環境因子といった具合です。
ICFを使う目的は分類することではありません。
観察した情報がどこに位置づくのかを明確にすることで、
次にどこへ介入するかの判断がしやすくなる点にあります。
観察の軸が一本になることで、評価や記録への展開もスムーズになります。
観察から判断が生まれる思考プロセスを3段階で整理する

観察が判断につながらないと感じる場面では、思考の途中が抜け落ちていることが少なくありません。
観察から判断までには、いくつかの段階があります。
この章では、その流れを3段階に分けて整理し、どこでつまずきやすいのかを明確にします。
第一段階|事実として見る(表情・姿勢・動作・反応)
最初の段階で重要なのは、解釈を入れずに「事実として見る」ことです。
この時点では、良い・悪い、できている・できていないといった評価は行いません。
例えば、
-
表情が硬い
-
視線が合いにくい
-
立ち上がりで一瞬止まる
-
声かけに対する反応が遅れる
これらはすべて事実です。
「意欲が低い」「怖がっている」といった言葉は、すでに解釈が入っています。
事実と解釈が混ざると、後の判断がぶれます。
まずは、誰が見ても再現できるレベルで事実を拾うことが、観察の土台になります。
第二段階|意味づけする(なぜそうなっているか)
次の段階では、拾った事実に対して意味づけを行います。
ここで初めて、「なぜこの反応が起きているのか」を考えます。
例えば、
立ち上がりで一瞬止まるという事実に対して、
-
下肢筋力の不足
-
動作手順の混乱
-
失敗経験による恐怖感
といった複数の仮説が考えられます。
この段階で大切なのは、一つに決めつけないことです。
観察は答えを出す作業ではなく、可能性を広げる作業です。
意味づけができると、次にどこを追加で観察すべきかも自然に見えてきます。
第三段階|次の一手を選ぶ(介入・声かけ・待つ)
最後の段階が判断です。
意味づけされた仮説をもとに、「今、何を選ぶか」を決めます。
ここでの選択肢は、必ずしも介入することだけではありません。
-
声かけの内容を変える
-
環境設定を調整する
-
あえて待つ、見守る
といった判断も、立派な次の一手です。
観察が判断につながらないと感じるときは、
第三段階まで進まず、第二段階で止まっていることが多くあります。
「考えて終わり」ではなく、「選ぶ」まで進めることで、観察は臨床の力になります。
観察が「次の一手」に変わるOTの具体的な視点

観察が判断に変わるかどうかは、「何を見るか」ではなく「どう使うか」で決まります。
この章では、現場でよく迷いやすいポイントを軸に、観察を次の一手へ変える具体的な視点を整理します。
動作・姿勢・視線から読み取るポイント
動作や姿勢の観察は、多くのOTが意識しているポイントです。
しかし重要なのは、うまくできているかどうかよりも「どこで迷っているか」「どこで止まっているか」です。
例えば、
-
動作の途中で一瞬止まる
-
姿勢を整える前に動き出す
-
視線が次の対象に向かない
こうした特徴は、身体機能だけでなく、動作理解や予測の問題を示している可能性があります。
この視点を持つと、単なる反復練習ではなく、
環境調整や声かけの工夫といった選択肢が見えてきます。
動作の結果ではなく、過程を見る意識が、観察を判断につなげます。
表情やしぐさに現れる感情と変化の捉え方
表情やしぐさは、数値化しにくいため軽視されがちですが、
実際には介入の方向性を決める重要な情報源です。
例えば、
-
声かけ前後で表情がわずかに緩む
-
動作の直前に視線を逸らす
-
失敗後に動きが止まる
これらは、課題に対する感情的な反応を示しています。
感情の観察は、「分かったつもり」で終わりやすい領域です。
だからこそ、変化の前後をセットで見ることが重要です。
変化が起きたタイミングを捉えることで、声かけや課題設定の修正点が明確になります。
「今は介入しない」という判断が必要な場面
観察が深まるほど、「あえて介入しない」という選択が必要な場面も増えてきます。
しかし、この判断は新人ほど不安を感じやすいポイントです。
介入しない判断は、何もしないことではありません。
利用者が自分で試行錯誤できる余白を守る行為です。
例えば、
動作に時間がかかっていても、安全が保たれており、
本人が状況を理解しようとしている場合、
声かけを控えることで主体性が引き出されることがあります。
この判断ができるかどうかは、
「今何が起きているか」を観察できているかにかかっています。
待つことも介入の一つだと理解すると、観察の価値がより明確になります。
記録・目標設定につながる観察情報の整理方法

観察ができているはずなのに、記録や目標設定になるとうまく書けない。
この悩みは、観察そのものではなく「整理の段階」でつまずいていることが原因です。
この章では、観察を臨床に残すための整理方法を具体的に解説します。
評価と観察の違いを言語で分けるコツ
観察と評価が混ざると、記録は一気に分かりにくくなります。
観察は事実、評価は意味づけや判断です。
例えば、
「立ち上がりが不安定である」は評価に近い表現です。
一方で、
「立ち上がり時に膝伸展前に体幹が前方へ崩れる」は観察です。
この違いを意識するだけで、記録の精度は大きく変わります。
まず観察として事実を書き、その後に評価として解釈を書く。
この順番を守ることで、読み手にも思考の流れが伝わります。
記録に書ける観察・書けない観察の境界線
すべての気づきが、そのまま記録に適しているわけではありません。
記録に書ける観察には共通点があります。
それは、
-
他者が読んでも状況を想像できる
-
行動や反応として具体化されている
-
時間や場面が明確である
という点です。
「やる気がなさそう」「集中していない」といった表現は、
観察として感じていても、そのままでは記録に向きません。
代わりに、どの場面で、どのような反応があったのかを言語化します。
この整理ができると、観察は主観ではなく、共有できる情報になります。
目標設定と見立てに使える観察の残し方
観察が目標設定に活きない場合、
多くは「変化の方向性」が記録に残っていません。
例えば、
-
声かけ後に動作がスムーズになった
-
環境調整で反応が安定した
こうした変化は、目標設定の重要なヒントです。
目標は結果だけでなく、過程の延長線上に置くことで現実的になります。
観察した変化を残しておくことで、
「どこに介入すれば伸びるのか」という見立てが明確になります。
観察力が伸びるOTに共通する習慣と考え方
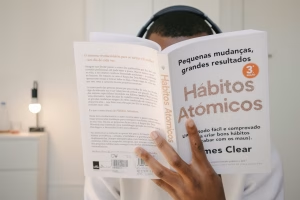
観察力は、特別な経験や才能によって身につくものではありません。
日々の関わりの中で、どのように考え、振り返っているかによって積み重なっていきます。
この章では、観察が安定して臨床に活きているOTに共通する習慣と考え方を整理します。
判断基準を自分の中に蓄積する方法
観察力が伸びているOTは、「正解」を探すよりも「判断基準」を増やしています。
一つひとつの場面で、なぜその判断を選んだのかを自分なりに言語化している点が特徴です。
例えば、
なぜ今回は声かけをしたのか、
なぜ今回は待つ判断を選んだのか。
この理由を曖昧にせず残しておくことで、次の似た場面で迷いが減ります。
判断基準は、成功体験だけでなく、うまくいかなかった経験からも蓄積されます。
観察は、その判断基準を更新するための材料でもあります。
振り返りで観察を「力」に変える視点
観察が力になるかどうかは、振り返りの質に左右されます。
単に「できた」「できなかった」で終わる振り返りでは、観察は積み上がりません。
有効なのは、
-
何を見て、どう判断したか
-
その判断は妥当だったか
-
別の選択肢はあったか
という視点で振り返ることです。
このプロセスを繰り返すことで、
観察 → 判断 → 結果のつながりが明確になり、
次回の観察がより目的を持ったものに変わります。
観察を武器にするOTが大切にしている姿勢
観察を臨床の武器にしているOTは、
「見落とさないこと」よりも「急がないこと」を大切にしています。
すぐに介入しない、結論を急がない。
その姿勢が、利用者の反応や変化を丁寧に捉える余白を生みます。
観察とは、相手を信頼し、状況を信じて待つ姿勢でもあります。
この姿勢があることで、観察は単なる技術ではなく、
作業療法らしい関わり方として深まっていきます。
まとめ

この記事のポイント
-
観察が苦手だと感じる原因は、センスではなく目的と構造の曖昧さにある
-
観察は情報収集ではなく、判断につなげるための材料である
-
事実を見る・意味づけする・次の一手を選ぶという段階整理が重要
-
待つ・介入しない判断も、観察に基づく立派な選択である
-
観察は振り返りを通して判断基準として蓄積されていく
総括
作業療法における観察は、特別な能力ではありません。
何のために見ているのかを意識し、判断までつなげる構造を理解することで、誰でも磨いていくことができます。
今日の臨床で見た一つの反応を、次の判断につなげる視点から振り返ってみてください。
その積み重ねが、観察を確かな力に変えていきます。



コメント